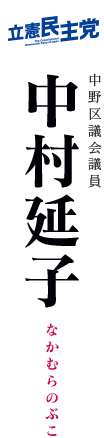第二回定例会で行った一般質問の概要
先日行った一般質問の概要版と、それに対する答弁をまとめました。
なお、正式な答弁は区議会HPの議事録が出るまでお待ちください。
1.行政報告について
(1) 中野駅新北口駅前エリア再整備事業について
(2) その他
2.次期基本計画について
(1) 財政運営について
(2) スマートウェルネスシティの推進について
(3) その他
3.RSウイルス感染症について
4.国際交流について
5.その他
1.行政報告について
Q 好調な財政状況にも恵まれ、当初のスキームと同じである必要はなくなった。今後の見直しにあたっては、区民が未来のまちづくりを楽しみに思えるコンセプトを掲げ、進めていくべきでは。
A タウンミーティングや意見交換会など対話を十分に重ねて、現在の再整備事業計画を一部見直していきたい。
Q今後は、再整備事業のスキームも含めてサウンディング調査を行っていく予定だが、区として優先順位をどこに置いて決定をしていくのか。
A 区民にとって特別な場所であり、100年先でも中野区の顔として愛され親しまれるようすべき場所だということを最優先に必要な判断をする。
Q当初の募集要項では、多目的ホールのみが、民設民営と明記されていた。子ども施設や展望施設は、そもそも施工予定者の提案であり、区が求めたものではない。このエリアにどのような機能が必要なのか改めて検討が必要。また、ホール以外の機能についても、事業者による整備所有運営を求めていくべきと考えるがどうか。
A ホール以外の施設においても、民間の創意工夫も含めて検討していきたい。
Q現在の区有施設整備計画には権利床として取得し、財源確保を目的とした資産の有効活用を図るとしている。この考え方を踏襲してくのか。将来的な施設更新費を考慮した持ち方を検討していく必要がるがどうか。
A 区有地等資産活用の考え方についても見直す必要があると考えている。具体的な考え方は、総合的に検討する。
Q今後の施設に関する区民の意見聴取については、幅広い区民の方々からの意見を聞ける仕組みの検討が必要と考えるがどうか。
A 開催頻度・開催場所・形式等を工夫してより多くの区民から意見を得やすい環境づくりにも努める。
Q今後の事業者選定では、事業成立性や概算事業費についても公募要件に加える事を検討すべきと考えるがどうか。
A 事業の成立性は重要であると考えている。公募時に求める事業成立性や概算事業費はサウンディング調査により社会情勢を踏まえて公募要件を整理する中で検討をする。
Q協定のあり方がどうだったのかの検証も必要。当初提案を守ってもらう仕組み、また区がイニシアチブをとれるような協定のあり方が求められると考えるがどうか。
A 今般の見直しに至った経緯から昨今の厳しい社会情勢においても事業を円滑に推進できるよう協定締結のあり方など必要な検討を行う。
Qサウンディング調査や、公募要件の見直し等、現段階で見込めるスケジュールの見込みは。
A 年内を目途に民間事業者へ調査を行い、年度末を目途に計画の見直し素案をまとめていく。
2.次期基本計画について
(1)財政運営について
Q 財政運営の考え方についてについて、区としてどのように物価高騰分を考慮し積み立てていくのか伺う。
A 今後、物価変動の影響などを考慮した見直しを検討しまとまり次第示したい。
Qこれまで施設類型ごとの標準規模を持つ事を求めてきた。区有施設整備計画の中で、延べ床面積をコントロールできるようになることに加え、財政的にも基金計画との連動が可能になると考えるがどうか。
A 一律に標準規模を決める事は難しい。一方で、工事費は引き続き高騰しており、対策は必要なことから新築や改築を行う際の床面積等について全庁的に共有し確認する場を設けることを検討したい。
Q学校施設の建て替えを着実に行っていくために義務教育施設整備基金の積み立ては着実に行う必要があるが、今後多くの施設が更新を迎える中で他基金も積み立てが充分ではない。財政運営の考え方の中で余剰分についてどうしていくのか伺う。
A 一般財源の確保ができた場合の積み立て方については見直しを検討し、令和8年度予算編成に反映したい。
Q 年度間調整分の規模を変更することにより、その分を義務教育施設整備基金や社会福祉施設整備基金に積み増しも可能になる。財政調整基金の年度間調整分の規模についても見直しが必要と考えるがどうか。
A 規模の妥当性については他自治体の状況や過去の実績などを勘案して見直しの検討を行いたい。
Q次期基本計画にあわせて財政フレーム示すが、今後の物価高騰をどのように考慮し、財政フレームに反映していくのか。
A 次期基本計画の財政フレームについても物価高騰をより適切に反映できるよう工夫し計画の実現性を確保する。
Q 今回、区が中野駅新北口エリア再整備事業の施工予定者と協定解除をする事の財政フレームへの影響はどの程度なのか。
A 歳入・歳出ともに令和7年度予算編成には見込んでおらず財政フレームの影響はない。再開発後に権利床で得るはずだった賃料については財政フレームへ反映しておらず、影響はない。
Q 次期区有施設整備計画では、施設の建て替え期間を長寿命化が可能であると判断された場合は大規模改修を行った上、建築後80年で建て替えとすることした。この方針変更による、財政フレームへの影響は。
A 長寿命化した場合、費用は後年度負担となり平準化されると想定している。長期間をみると長寿命化は解体費用の減も含め、財政面での効果があると考えている。
(2)スマートウェルネスシティの推進について
Q 基本計画改定にあたっては、SWCを重点プロジェクトに位置付ける事もひとつの選択肢と考えるがどうか。
A 次期基本計画における重点プロジェクトのひとつである「地域包括ケア体制の実現」の中に位置付けていくことを考えている。
Q区が目指すべきウォーカブルなまちづくりの目指すべき姿の共通目標を持ち、その目標にむけた施策を基本計画に落とし込んで進めていくべきと考えるがどうか。
A 次期基本計画では、施策の1つに「歩きたくなるまちづくりの推進」を位置づけ、全庁的な共通理念として区の様々な事業に反映していきたい。
Q区は九州大学と地域包括ケア推進パートナーシップ協定を結び、医療や介護、健診といった健康関連のデータを九州大学に提供、データ分析によるフィードバックにより健康寿命の延伸や健康格差の解消など、区民の健康増進を図ることを目指している。SWCで具体的にどのように活用していくのか。
A 今後立ち上げていくSWCプロジェクトに反映させたい。現在取り交わした「覚書」にはワクチン接種歴などの一次予防に関するデータは含まれていないが、今後分析内容などについて協議していく。
Q女性は初潮を迎える思春期から女性ホルモンの影響を大きく受け、生涯にわたり続く。将来的に子どもを産む、産まないに関わらず、プレコンセプションケアや包括的性教育は女性自身が自らの健康を維持していくために必要な知識であり、区として課題に取り組んでいくべきではないか。
A 女性の健康リテラシーを高めるSWCプロジェクトの1つとして、民間とも連携しながら取り組む。
Q女性はかかりつけ婦人科医を持つ事を推奨されているが繋がっていない。生理痛や過多月経など、人と比べることができない為に自分だけで問題を抱えがちです。思春期から医療につながる取組を検討していくべきと考えるがどうか。
A 思春期を視野にいれた、かかりつけ婦人科医の推奨を検討したい。
3.RSウィルス感染症について
Q RSウイルスは初感染乳幼児の場合は重症化することがあり、近年の研究では感染した2歳未満の乳幼児のうち25%が入院していた。日本におけるRSウイルス感染症による小児の死亡数は、2008-2012年の5年間で、年間平均31.4人とも報告されている。まずはRSウイルス感染症についてと、ワクチンの存在を妊婦・高齢者ともに知っていただく事が必要だと考えるがどうか。
A 区HPにおいてRSウイルス感染症の特徴や主な症状、予防対策およびワクチン接種について周知しており、今後も広報の工夫を図りたい。
Q医療費、おやの精神的負担や一定期間仕事にいけない経済的影響、もちろん未来ある子どもを守るという観点からも、区として妊婦へのRSウイルスワクチンの一部助成を実施するべきと考えるがどうか。
A 実施に向けて中野区医師会等と協議・検討していく。
4.国際交流について
Q 台北市中山区との交流について、相互に行き来できる仕組みなど、未来ある事もたちが交流を通じて相互理解を深め友好関係を続けていけるような仕組みづくりの検討が必要ではないか。
A 教育委員会とも連携しながら検討していきたい。
第2回定例会で一般質問を行いました!
6月2日から始まった第2回中野区議会定例会で一般質問を行いました。
質問原稿は以下になります。
1.行政報告について
(1) 中野駅新北口駅前エリア再整備事業について
(2) その他
2.次期基本計画について
(1) 財政運営について
(2) スマートウェルネスシティの推進について
(3) その他
3.RSウイルス感染症について
4.国際交流について
5.その他
令和7年第2回定例会にあたり、立憲・国民・ネット・無所属議員団の立場から一般質問を行います。質問は通告の通りで、その他はございません。
1.行政報告について
一昨日、本来は予定のなかった議会日程を追加して、中野駅新北口駅前エリアのまちづくりについて、区長からこれまでの経緯や今後の取組について行政報告がありました。中野区は3月に、①事業成立性の見通しが明らかではなかったこと、②当初の提案内容が十分継承されておらず、公平性・中立性の観点から課題があること、③区民が利用する施設の魅力が認可申請時に区が同意した事業計画と比較して低下していることを理由に、施工予定者との協議を継続せず、協定解除へと舵を切りました。
今回、区が一旦立ち止まる決断をした事は賢明な判断だったとも言えます。第2回定例会には、協定解除の議案が提案されています。協定解除にはすべての地権者の合意が必要であり、区と施工予定者だけで進められるものではありませんでした。3月に施工予定者との協議を継続しないと決定してから、どのような手続きが必要だったのか、また、課題となってきたのか伺います。
もともと、中野駅新北口駅前エリア再整備事業では、新区役所の建設費用等を賄う予定でした。施工認可申請の取り下げを行ってからは、転出補償金が入ってくる見込みがなくなったことで、昨年度に45億、残りの71億を5年間にわたり償還することでカバーする事としています。好調な財政状況にも恵まれ、転出補償金をこの費用にあてる必要が現状ではなくなり、当初のスキームと同じである必要はなくなりました。白紙になったからこそ色んな選択肢があります。例えば、グラングリーン大阪は、「みどり」と「イノベーション」の融合をコンセプトに、大規模ターミナル駅である梅田駅前に約45,000㎡もの大規模都市公園をつくることを公民連携の枠組みの中で決め、公園を中心とする大規模複合再開発が行われました。行政や民間で行われる近年の再開発のコンセプトは「みどり」がトレンドですが、ウェルビーイングをコンセプトにするものも多く存在します。また、下北沢駅前再開発の「ミカン下北」のように、そのまちの特徴を生かしたコンセプトを掲げて行われるものあります。今後の見直しにあたっては、区民の皆さんが未来のまちづくりを楽しみに思えるコンセプトを掲げ、中野駅新北口駅前エリアのまちづくりを進めていくべきと考えますがいかがでしょうか。今後は、定期借地で行うのか、市街地再開発事業で行うのか、再整備事業のスキームも含めてサウンディング調査を行っていく予定とのことですが、区として優先順位をどこに置いて決定をしていくのか、伺います。
区長は「中野駅前のシンボル拠点とはどのような施設なのか」「にぎわいと交流を作り出すためにはどのような施設が必要なのか」「未来を担う子どもたちのために必要とされるのは、どのような施設なのか」といった視点で検討していくと述べられました。当初の募集要項では、多目的ホールのみが、整備・誘導方針として民間事業者による整備・所有・運営が明記されていました。子ども施設や展望施設は、そもそも施工予定者の提案で出て来た機能であり、元々区が求めたものではありません。子ども施設、バンケット、ホテル機能、展望施設など、区としてこのエリアにどのような機能が必要なのか改めて検討が必要です。また、ホール以外の機能についても、事業者による整備所有運営を求めていくべきと考えますがいかがでしょうか。見解をお示しください。
現在の区有施設整備計画には「権利変換により保有する資産については、権利床(土地及び床)として取得するものとし、民間事業者への貸付など行政サービスの財源確保を目的とした資産の有効活用を図ります。」としています。この考え方を踏襲してくのかの検討も必要になります。大きな施設になれば、将来的に施設更新費がかかってくるため、その分を考慮した持ち方を検討していく必要もあります。この点についても今後十分な検討が必要になると考えますが、いかがでしょうか。
今後の施設に関する区民の意見聴取について伺います。5月28日と6月1日に区民説明会を行いました。初回は約80人が参加され、2回目は約70人が参加されたと伺っています。7月以降も意見交換会などにより区民の方々からの意見を伺う事としています。幅広い区民の方々からの意見を聞ける仕組みの検討が必要です。基本構想・基本計画の時は無作為抽出により、参加者を募っていました。子どもの意見を聞くことも選択肢だと考えます。多くの方から愛される施設とするために工夫が必要だと考えますが、いかがでしょうか。見解を伺います。
より良い施設としていくためにも、これまでの検証は必要だと考えます。施工予定者の当初提案は、資金計画の確実性を指摘されていました。物価高騰の影響も大きく影響をされたことも一因ですが、結果的に認可申請を取り下げる事になってしまいました。今回の経緯を鑑みても、事業の成立性は非常に重要であり、サウンディング調査でもこういった点を十分にヒアリングし、事業スキームの検討に努めていただきたいと考えます。また、今後の事業者選定に当たっては、事業成立性や概算事業費といった点についても公募要件に加える事を検討してはいかがでしょうか、伺います。
協定のあり方がどうだったのかの検証も必要です。今後の事業者選定後にはその反省点を活かした仕組みを検討していくべきと考えます。令和3年に施工予定者と協定書を締結する以前から、わが会派の酒井議員から当初提案を継承してもらう実効性のある協定とするべきと再三指摘をして来ました。当初提案を守ってもらう仕組み、また区がイニシアチブをとれるような協定のあり方が求められます。区の見解を伺います。
スケジュールについても伺います。昨年10月に認可申請が取り下げられなかった場合は、令和11年度には再開発事業が竣工を迎える予定となっていました。認可申請の取り下げが行われた際には、3年ほどの遅れの見込みとの見解でした。物価高騰の将来予測が難しい中では、竣工までのスケジュールは見通せなかったとしても、どれくらいの期間でサウンディング調査や、公募要件の見直し、公募が行われるのか等、現段階で見込めるスケジュールについて、区の見解をお示しください。伺いまして次の質問に移ります。
2.次期基本計画について
(1)財政運営について
まず、財政運営の考え方についてについて伺います。令和5年度から採用されている財政運営の考え方についても改めて考え方を整理し、次期基本計画とあわせてお示しをいただけると区はこれまで答弁されてきています。具体的には、現在は各施設整備基金に減価償却費相当の25%を積み立てているにとどまっているところに、どのように物価高騰分を上積みしていくのかが大きな課題だと認識しています。例えば、学校施設の建て替えは、1校あたり50億円としてきましたが、72億円とのご答弁もありました。減価償却費相当の25%だけでは、現在の急激な物価高騰に対応する十分な整備費用を確保することが困難になってしまうのではないかと懸念しています。区としてどのように物価高騰分を考慮し積み立てていくのか、伺います。
これまで、施設類型ごとの標準規模を持つ事を求めてきました。区有施設整備計画の中で、延べ床面積をコントロールできるようになることに加え、財政的にも基金計画との連動が可能になると考えます。安定した財政運営を行っていくためにも必要と考えますが、いかがでしょうか。改めて伺います。
財政運営の考え方の中では、「財政状況により、更に一般財源の確保ができた場合は、義務教育施設整備基金への積み立てを行う」としています。学校施設の建て替えを着実に行っていくためには、義務教育施設整備基金の積み立ては着実に行っていく必要があると考えます。また、今後多くの施設が更新を迎える中では、例えば社会福祉施設整備基金も積み立てが充分とは言えない状況です。こうした状況を鑑み、これらの考え方についても改めて検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
財政調整基金の年度間調整分の規模についても検討が必要です。これまでリーマンショックや東日本大震災、コロナなど、緊急事態となった際にも、財政調整基金が目減りしたことはありませんでした。規模を変更することにより、その分を義務教育施設整備基金や社会福祉施設整備基金に積み増しも可能になります。年度間調整分の見直しについても積み立ての考え方とあわせて検討すべきと考えますが、区の見解をお示しください。
次に財政フレームについて伺います。次期基本計画にあわせて、財政フレームをお示しいただくこととなりますが、昨今の物価高騰の影響は、施設整備費だけにとどまらず、委託料や指定管理料等にも及んでいます。今後の物価高騰をどのように考慮し、財政フレームに反映していくのか伺います。
今回、区が中野駅新北口エリア再整備事業の施工予定者と協定解除をする事の影響はどの程度なのか伺います。入ってくる予定だった転出補償金はもとより、今後再開発後に権利床で得るはずだった賃料など、財政フレームへの影響はどの程度か伺います。
区有施設整備計画では、施設の建て替え期間について、建築後60年を迎える前に建物耐久度調査等を実施し、長寿命化が可能であると判断された場合は大規模改修を行った上、建築後80年で建て替えとすることしました。この方針変更による、財政フレームへの影響をどのように考えているのでしょうか。調査や長寿命化の工事にも一定の費用はかかってくる為、年次に落としていく段階で影響が出てくる可能性もあると考えますが、区の見解をお示しください。
今年の予算特別委員会では、財政フレームを現在10年間で出しているところも見直していいのではと申し上げました。後年度は事業が具体化しない中では、概算でしか財政フレームに載せる事ができないためです。例えば、学校施設整備計画は、学校施設の改築が具体化された時点で設計費用や整備費用などが財政フレームに影響する事が予想されます。中々将来予測が難しい中では、計画期間の5年間とあわせる事も選択肢だと考えます。また、令和8年度予算編成と基本計画策定段階では、なるべく差異が出ないようつとめるべきですが、いかがでしょうか。差異が出てしまったとしても、丁寧に説明を尽くす事が必要と考えますが、いかがでしょうか。
(2)スマートウェルネスシティの推進について
区は、3月の厚生委員会に「スマートウェルネスシティ中野構想(案)について」を報告されました。その中で、基本構想と基本計画等との関係を「次期基本計画では、各施策に共通する理念のひとつとして捉えるとともに、全庁的なSWC推進会議のもと、方向性を確認しながら推進していきます」としています。基本構想・基本計画・個別計画と体系が明確ですが、SWC中野構想については、そのどこに位置づけられているのか曖昧です。位置づけが明確なものとならないと、推進をしていくのにあたり継続性が担保できないとも考えます。次期基本計画では、位置づけを明確にするべきと考えますがいかがでしょうか。基本計画改定にあたっては、重点プロジェクトに位置付ける事もひとつの選択肢と考えます。見解をお示しください。
SWC中野では、施策の方向性として1.健康づくり=ヘルスリテラシーの向上、2.つながりづくり=ソーシャルキャピタルの醸成、3.まちづくり=歩きたくなる魅力あるUDまちづくりの3つを掲げられました。「川上」予防を目指すとしている中では、これまでの健康施策にとどまらない全庁的な推進体制が不可欠です。区が目指すべきウォーカブルなまちづくりとは、どういうものなのか。目指すべき姿の共通目標を持ち、その目標にむけた施策を基本計画に落とし込んで進めていくべきと考えます。区の見解をお示しください。
次に推進体制について伺います。現在、SWCは地域包括ケア担当が所管ですが、さまざまな部署との連携が求められています。とりわけ、「健康づくり」の中では、保健企画課のデータヘルス計画の活用が必須だと考えますが、現在の連携体制はどうなっているのか、伺います。今後の推進体制の中では、保健所の役割も明確にしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
2月28日に区は九州大学と地域包括ケア推進パートナーシップ協定を結びました。4月17日には覚書を交わしたと伺っています。今回の協定は、区が医療や介護、健診といった健康関連のデータを九州大学に提供することで、健康寿命の延伸や健康格差の解消など、区民の健康増進を図ることを目的として締結しました。九州大学の行っているライフスタディは、地域住民の健康増進に貢献することをミッションに、自治体のデータを活用し、基盤整備、研究者との連携体制の構築、エビデンスに基づいた政策立案のためのエコシステムの開発を行っています。フィードバックにより、地域別の健康状態の可視化やハイリスク者の検索機能などもあり、国民健康保険や健診のデータを基に介護予防につなげていくことも可能です。まず今回の協定締結により、医療や介護、健診といったデータを提供するとのことですが、そこにワクチン接種履歴などの一次予防データは含まれるのか伺います。今後、九州大学のデータ分析をSWCで具体的にどのように活用していくのか区の見解をお示しください。中野区よりも以前から活用されてきた自治体の例も参考に、データ分析と施策展開について積極的に進めていくべきと考えますがいかがでしょうか。こうしたデータ分析による施策展開は区民の健康増進はもとより、結果的に医療費削減という効果も期待できると考えます。見解をお示しください。
SWC中野構想の中では、中野区が目指すSWCとして、「健康状態を川に例えた時の“川下”における対処やハイリスク対応の体制を整備しつつ、“川上”における予防に力点を置く」としています。「川上」のゼロ次予防を目指すのであれば、若い世代への健康情報の提供や教育が必要になると考えます。とりわけ、女性の生涯にわたる健康維持には、若いころからのケアが重要です。女性は初潮を迎える思春期から女性ホルモンの影響を大きく受け、それは妊娠期や更年期など生涯にわたり続きます。現在、若年女性のやせの問題もあります。将来的に子どもを産む、産まないにかかわらず、プレコンセプションケアや包括的性教育は女性自身が自らの健康を維持していくために必要な知識であり、情報格差による健康格差につなげない為にも区として取り組んでいくべき課題だと認識していますが、見解を伺います。プレコンセプションケアの推進は、学校や子育て支援、産前産後ケアなど、女性のライフステージそれぞれに関わってきます。SWCとして、進めていく必要があると考えますが、区の認識を伺います。
さきほど、女性は人生で生涯にわたり女性ホルモンの影響を受け続けると申し上げましたが、だからこそ、かかりつけ婦人科医を持つ事を推奨されています。一方で、なかなかそこに繋がっていません。生理痛や過多月経など、人と比べることができない為に自分だけで問題を抱えがちです。生活を普段通りに送る事が困難になるほど重症な方もいらっしゃいます。生理痛は直せる、という事を知らない方も多いです。こうした現状を鑑みて、思春期から医療につながる取組を検討していくべきと考えますが、区の見解を伺います。
(3)その他
3. RSウィルス感染症について
RSウイルスは、一般的には乳幼児の呼吸器感染症の原因ウイルスとして知られています。2歳までにほぼすべての子どもが感染するとされていますが、その後も生涯にわたって何度も感染と発症を繰り返します。通常、健康な成人は感染しても軽症で、多くは風邪のような症状で自然軽快します。一方、初感染乳幼児の場合は重症化することがある事もわかっており、RSウイルスに感染した2歳未満の新生児・乳幼児を対象とした近年の研究結果によると、感染した2歳未満の乳幼児のうち、25%が入院していたことがわかりました。入院した新生児・乳幼児の約90%では、重症化のリスク因子はありませんでした。また、入院した2歳未満の新生児・乳幼児の月齢は、6ヵ月未満の割合が約40%を占めていました。日本におけるRSウイルス感染症による小児の死亡数は、2008-2012年の5年間で、年間平均31.4人とも報告されています。また、高齢者や基礎疾患のある成人においても、RSウイルスは、肺炎などを引き起こすこともあります。肺炎による高齢者の入院は寝たきりや介護の問題も引き起こす事も報告されています。
こうした背景から、1960年代初期からRSウイルスワクチンの開発が進められ、2024年1月に高齢者のRSウイルスワクチンが販売となりました。また、妊婦へのRSウイルスワクチンは令和6年5月に販売が開始されました。妊婦へのワクチンは、妊娠24週から36週で接種するとお腹の中の胎児に抗体が移行し、新生児および乳児のRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防をするとしています。
令和7年度は、妊婦対象のRSウイルスワクチンに対する助成制度を、静岡県袋井市や千葉県いすみ市など20自治体が、高齢者対象を石川県かほく市など5自治体が導入しています。現在、東京都の自治体では妊婦・高齢者ともに導入されていません。知り合いの産婦人科医いわく、現在自費で打つ妊婦の多くは2人目以降を妊娠中の方との事で、それは、RSウイルスの怖さを知っているからではないかと推測できます。まずはRSウイルス感染症についてと、ワクチンの存在を妊婦・高齢者ともに知っていただく事が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
また、医療費、おやの精神的負担や一定期間仕事にいけない経済的影響、もちろん未来ある子どもを守るという観点からも、区として妊婦へのRSウイルスワクチンの一部助成を実施するべきと考えますが、いかがでしょうか。妊娠間隔と接種頻度の関係など、課題を整理する必要もありますが、その上で実施に向けた具体的な検討をしていくべきと考えます。区の見解をお示しください。
4.国際交流について
台北市中山区との交流について伺います。4月15日から17日まで、中野区議会日台議連の一員として台北市を訪問してきました。台北市政府、台北市議会、台湾日本関係協会、そして、台北市中山区を訪問し、交流をしてまいりました。2019年1月に酒井区長とともに公式訪問してから6年の月日が経過してしまいましたが、議連会長のご尽力もあり、台北市政府、台北市議会、中山区とどこもこれまで以上の大歓迎でお迎えいただきました。さらには、今後の具体的な交流につながる話し合いをしたいとの申し出もあり、非常に実りの多い訪問となりました。
区として、今後の中山区との交流をどのように進めていく事を検討しているのか伺います。中野区内で行われるイベント等に今度は台北市中山区に来訪いただくことも必要と考えますが、いかがでしょうか。早期にその準備を進め、具体的日程調整を行うべきと考えます。また、今後の中山区との交流にあたっては、行政間の交流にとどまらず、市民交流につなげていく仕掛けが必要です。興味関心の高いアニメや、また防災連携などテーマを持って交流をしていくこと、更には、子どもたちの交流につながるよう進めていくべきと考えますが区の見解をお示しください。具体的には、ウェリントン子ども交流事業のように、相互で行き来できる仕組みや、オンラインを使った交流など、未来ある子どもたちが交流を通じて相互理解を深め友好関係を続けていけるような仕組みの検討が必要と考えます。区の見解をお示しください。お伺いし、私のすべての質問を終わります。
アーカイブ
- 2026年2月
- 2025年6月
- 2025年2月
- 2024年11月
- 2024年4月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年6月
- 2022年2月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2020年6月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2017年12月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月